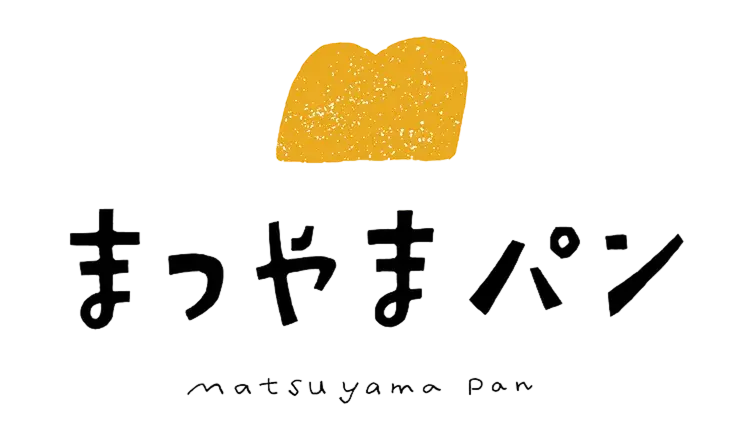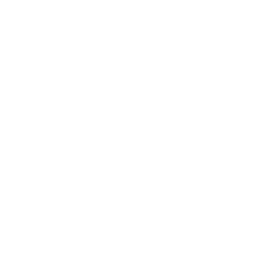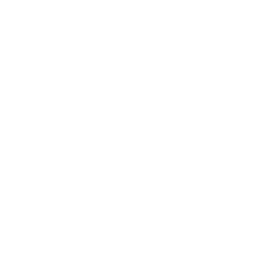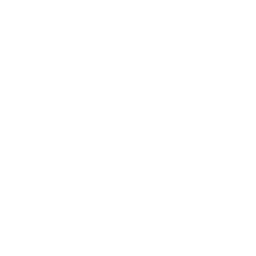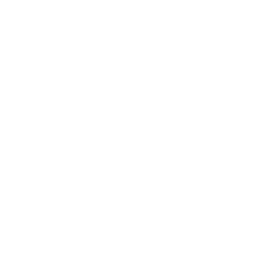パン生地は生きている──発酵の中で起きている小さな奇跡
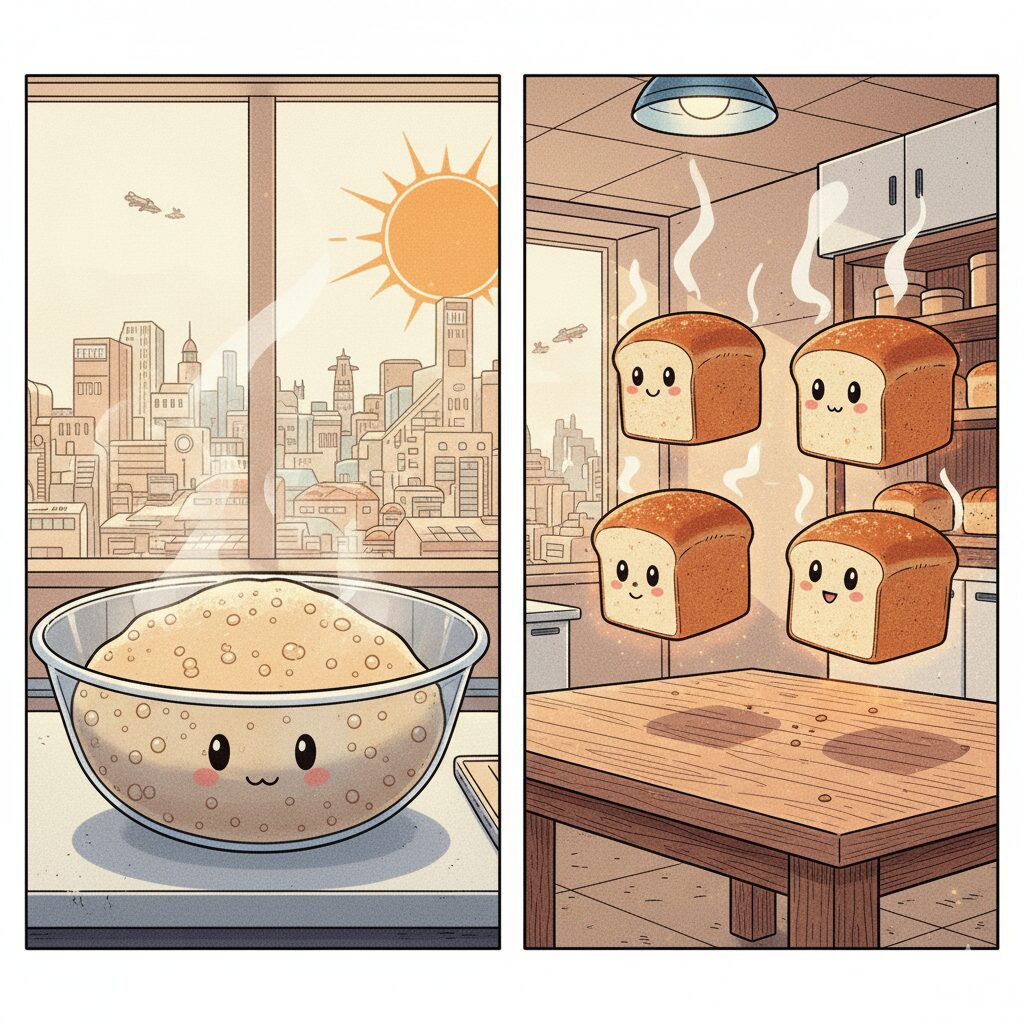
パン作りをしていると、「発酵」という言葉を毎日のように口にする。
けれど、この一語の中には驚くほど多くの生命現象が詰まっている。
発酵とは、酵母(イースト)が糖を食べ、炭酸ガスとアルコールを生み出す過程。
つまり、パンは生きながら自らを膨らませていく生物のような存在なのだ。
🧬 酵母という小さな職人
パンの発酵を担うのは酵母菌。
彼らは顕微鏡でしか見えないほど小さいが、
生地の中では24時間365日働き者だ。
酵母は糖分を分解してエネルギーを得る。
その副産物が二酸化炭素とアルコール。
炭酸ガスは生地をふっくらと押し上げ、
アルコールは焼成時に香りへと変化する。
この「働き」がなければ、パンはただの焼き粉だ。
発酵とは、パンが“パンになる”ための生命反応。
生地の中で、見えない微生物たちが踊っている。
🌡️ 温度と時間──発酵のリズムを聴く
酵母は温度に敏感だ。
20℃ではゆっくり、30℃では活発に、35℃を超えると息切れを起こす。
だから職人は、生地を触るだけで“今の機嫌”を感じ取る。
「発酵の見極め」とは、科学というより感覚に近い。
少し冷たい日には毛布のように温め、
暑い日には影を作ってやる。
酵母の呼吸を感じながら、
パン職人は生き物と対話している。
🍞 二次発酵という“静けさの時間”
一次発酵でパンは命を得る。
二次発酵では、その命が整えられていく。
一次発酵が「膨らむための呼吸」なら、
二次発酵は「落ち着くための深呼吸」だ。
この過程を省くと、パンは内部が荒れ、食感が固くなる。
静けさの時間を与えることで、
グルテンが均一に伸び、香りが豊かになる。
つまり、良いパンには“間”がある。
それはまるで人間の成熟と同じだ。
焦っても、時間だけは焼き縮められない。
🔬 科学の中に宿る詩
パンの発酵を科学的に説明すれば、
酵母によるアルコール発酵とデンプン分解の化学反応にすぎない。
けれどその結果、生まれるのは香り、柔らかさ、温もり。
化学反応が“心地よさ”を作り出すのは不思議だ。
だからパン職人はいつも、
「生地が発酵している」のではなく
「発酵という時間が生地を育てている」と感じる。
🕰️ パンを育てるという考え方
発酵を“管理する”のではなく、“見守る”。
この意識の違いが、パンの味を分ける。
酵母は支配されるより、信頼される方がよく働く。
人間のチームワークと同じだ。
パンを焼くことは、時間と生き物のリズムを整える仕事。
だから職人はみんな少し優しい顔をしているのかもしれない。