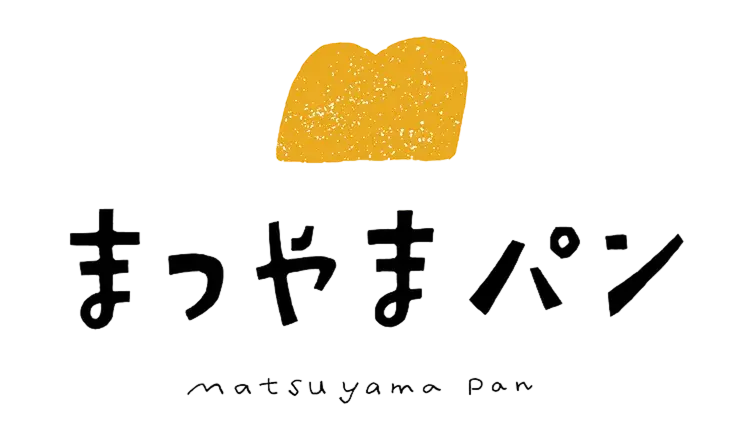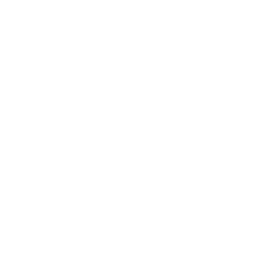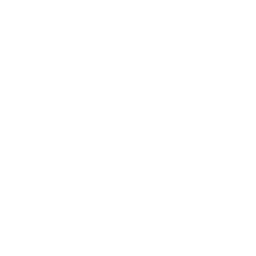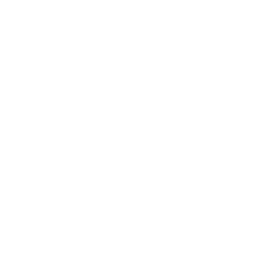国産小麦は本当にパンに良い?分析で語る正体

「国産小麦=おいしい」という思い込み
近年、パンの世界では「国産小麦使用」という言葉が品質の証のように使われることが増えています。
しかし実際のところ、国産小麦がパンづくりに本格的に使われるようになったのは、ほんの十数年前のこと。
しかも、それ以前の日本の小麦は「うどんや和菓子向け」が中心で、パンづくりには不向きな性質を持っていました。
それでも“国産”という言葉の響きが消費者の安心感を刺激し、
やがて「国産=おいしい」「外国産=添加物が多い」という構図ができあがったのです。
このイメージの裏側には、科学的な“グルテン構造”の違いという現実が隠れています。
日本の気候は小麦の育成に不利
小麦は気温が高すぎるとタンパク質がうまく形成されず、
グルテン(パンの骨格を作る弾性たんぱく質)が弱くなります。
つまり、湿度が高く夏が長い日本の気候はパン用小麦の栽培に向いていないのです。
北米やカナダ、オーストラリアがパン用小麦の生産に適しているのは、
冷涼で乾燥した気候が、たんぱく質を安定して形成するから。
日本ではその条件を人工的に補うため、
農研機構などが長年にわたり育種研究を進め、
ようやく「ゆめちから」や「春よ恋」といったパン向け国産小麦が登場しました。
しかし、これらも依然として製パン性(膨らみ・弾力・発酵耐性)では
外国産に及ばないというデータが多くあります。
“国産小麦パン”が膨らみにくい理由
パン生地の膨らみを支えるのは、グルテンの強さと弾力のバランス。
国産小麦はたんぱく質量が少なく、しかもグルテンの質(伸展性)が弱いため、
生地をこねても弾力が出にくく、
発酵中にガスを保持しにくい傾向があります。
結果として、
- ボリュームが出にくい
- クラム(内側)がやや密で重い
- 焼き色が淡く、香ばしさが控えめ
といった特徴が生まれます。
これは“悪い”というより、向き・不向きの問題。
ハード系やリーン(油脂少なめ)のパンには向きませんが、
しっとり系や菓子パンなどには独特のもっちり感が活きることもあります。
科学で見た「国産小麦ブーム」の副作用
国産小麦を推すパン屋が増えること自体は悪いことではありません。
問題は、“使う理由”が科学的裏付けよりもマーケティング先行になっている点です。
国産小麦100%と謳うと、消費者の共感は得やすい。
しかし、製パン科学の視点では、
「おいしさ=国産」ではなく、「目的に合った小麦を選ぶ」ことこそが本質です。
小麦の生化学を理解せず、イメージだけで選ぶことは、
まるで湿度の高い日にコートを着るようなもの。
パン職人に必要なのは「愛国心」より「適材適所の設計力」です。
国産小麦は「ようやく戦える素材」になった
近年の改良で、国産小麦の性能は飛躍的に向上しました。
製パン試験でも、外国産ブレンドに近いグルテン構造を持つ新品種が増えています。
これにより、パン職人は「味わいと香りで選ぶ時代」に入りつつあります。
香ばしさ・甘み・口溶けなど、外国産にはない“繊細な美味しさ”が国産には確かに存在する。
しかし、それを活かすには温度管理・発酵時間・水分量の微調整が不可欠です。
つまり、国産小麦は“万能素材”ではなく、“職人の技術があってこそ生きる素材”です。
まつやまパンの立場:素材は国産かどうかより「完成度」
まつやまパンでは、国産・外国産という線引きではなく、
どんな小麦がそのパンに最も合うかを基準に選定しています。
例えば、ふんわり軽いキューブパンには安定したグルテン力を持つ外国産を中心に、
風味を重ねたい甘系パンには国産小麦をブレンド。
どちらか一方に偏ることなく、“素材と技術の対話”でベストな結果を導き出します。
パンにとって国籍は問題ではありません。
“おいしさを再現できる条件”を見極めることが、職人の科学です。
まとめ|“国産”よりも“適正”を選ぶ時代へ
パンづくりの世界では、国産小麦はようやく本格的な選択肢の一つになりました。
ただし、それは「全てに勝る」ではなく、「条件が整えば活きる」素材。
パン職人にとって大切なのは、国産か輸入かではなく、
パンが最も美味しくなる環境をつくることです。
科学が教えてくれるのは、素材を愛するとは盲信しないこと。
まやかしを越えて、本当の“おいしいパン”を選ぶ時代が始まっています。