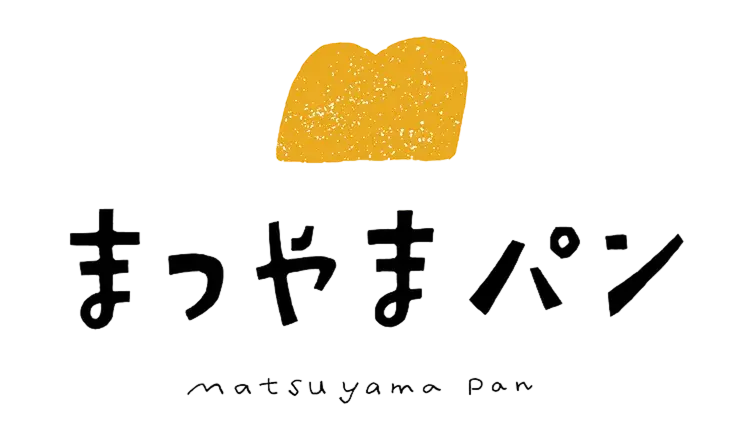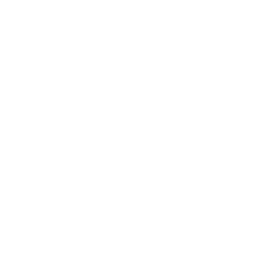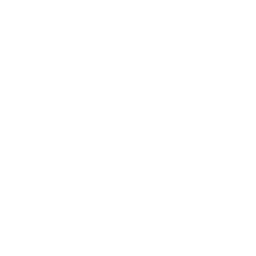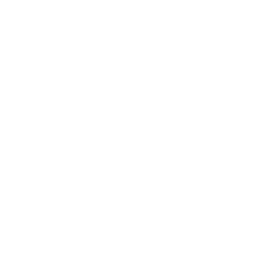最古のパンから紐解く人類パン好き説
最古のパンは人類をざわつかせたのか?
ヨルダン北東部で発見された炭化パン片は
人類学の世界に小さな波紋を広げた。
推定年代は約1万4千年前。
農耕よりも古い。
つまり、人類は麦を育てる前にパンを焼いていたことになる。
池田浩明氏の『パンビジネス』にある「最古のパンから紐解く人類パン好き説」という題名の魅力は、単なる文化論でなく、科学的事実がその背後にある点にある。
火・水・穀物。
この三つさえ揃えば、パンらしきものはできる。人類はこれを“うっかり発見”したのではない。“積極的に焼きたかった”のだという仮説が立ち始めている。

パンの魅力は化学反応に宿っている
最古のパン片を科学的に調べると、大麦や野草のデンプンが糊化し、メイラード反応による香りが微かに残っているという。発酵はしていないが、 “焼けた穀物の香り” というだけで十分に魅力的だったはずだ。
現代の製パン理論では、パンのおいしさの多くが「デンプンの糊化」と「褐変反応」によって説明される。つまり、パンの“基本の快楽”は、技術より先に自然現象として成立していた。
この現象は、最新のキューブパンにも当然受け継がれている。
形状がどう変化しても、パンをパンたらしめているのは、
この生物と化学の微妙なバランスだ。
1万4千年前の平焼きパンと、現代の四角いキューブパン。
距離はあっても、原理は驚くほど同じである。
人類は“偶然”を“技術”に変えた
やがて紀元前3000年頃、エジプトで自発的発酵が利用され始める。
生地を放置したら膨らんでしまった。ところが人類はこれを“失敗”と判断せず、むしろ積極的に利用した。柔軟さなのか、欲望なのか、この判断がパン文化を一気に進化させた。
発酵の登場はパンを“偶然の食品”から“設計できる食品”へ変えた。
- 軽さ
- 気泡構造
- 香り
- 膨らみ
これらをコントロールしようという意思が生まれた。
ここからパンは技術の領域に踏み込む。結果として人類は、自然の形に任せるのではなく、パンの「膨らみ方」「香り」「質感」を自分の好みに寄せ始めた。
キューブパンという“人類の偏愛”の最新形
人類はやがて、パンの形にまで介入し始める。
本来、パンは丸く膨らむはずなのに、現代では四角く焼かれたり、型に入れられたり、
内部の気泡が正方格子のように整っていることを評価するようになった。
キューブパンは、その極端な例だ。
膨らみを制御し、内部の気泡構造を均質化し、断面美を求める。
これはもはや料理ではなく、建築に近い。
なぜ人類はここまでパンに形を求めるのか。
仮説として、人類はパンそのものより「パンをつくれる自分」に欲望があるからだ。発酵を読み、温度を管理し、膨らみを設計し、四角形に閉じ込める。これは自然への介入の典型例であり、パンづくりは「世界を自分の意図通りに動かせる」という感覚を与える。
最古のパンを焼いた人たちは、気泡や形を気にしなかったが、
「焼いたら美味しくなる」という発見の快感は十分に味わっていたはずだ。
キューブパンを焼く現代人が求めるのは、より複雑化した同じ快感構造だ。
最古の炭片と現代のキューブパンは“一本の線”でつながっている
学術的にも、パン文化の進化は「食材」より「行為」に強く依存することが分かっている。焼く・膨らませる・形を整える。これらの行為が、人類に特有の創造性を刺激する。
最古のパン片は、その起点だ。
そしてキューブパンは、その延長線上にある“最新のパン文化の実験場”と言える。
パンは単なる食品ではなく、人類の創造性と介入欲の結晶だ。
1万4千年前の炭化した欠片を見ても、最新のキューブパンを見ても、人類がパンに惹かれる理由は案外変わっていない。“焼くと世界が少し扱いやすくなる”という単純な事実が、私たちの根底にある。