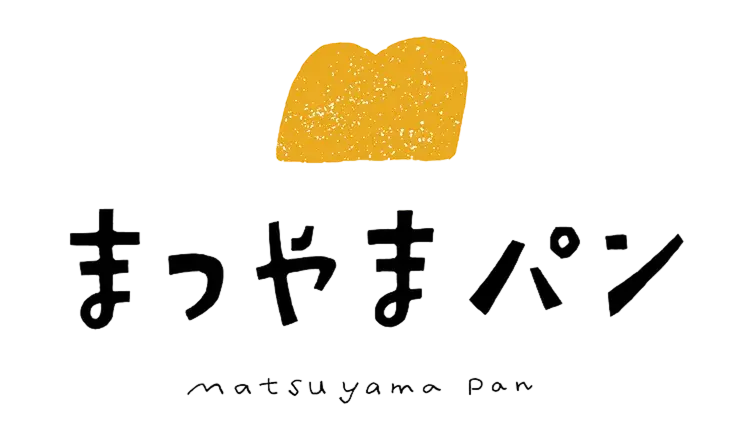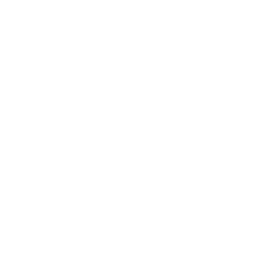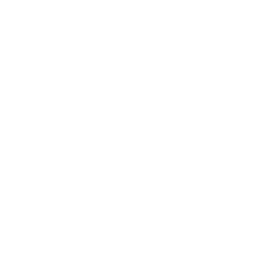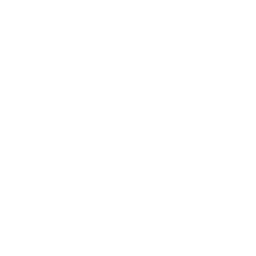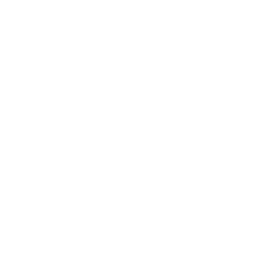焼き加減というあいまいな科学

パンを焼くとき、誰もが「焼き加減」という言葉を使う。
だが、この言葉をきちんと説明できる人はあまりいない。
強火なのか中火なのか、何分なのか。
温度を測る人もいるけれど、最終的には「見た目」と「匂い」に頼る。
つまり、**焼き加減とは理屈ではなく“気分の観測値”**だ。
オーブンの前でパンを見つめる時間は、だいたい哲学に似ている。
少し早い気もするし、まだ足りない気もする。
どちらの仮説も正しいし、どちらも間違っている。
パンは沈黙しているが、見ているこちらの心が落ち着かない。
この曖昧なやり取りの中で、人間は“判断”という名の妄想を働かせる。
焼きすぎれば「香ばしい」と言い訳し、
焼き足りなければ「しっとりしている」と慰める。
パン屋は失敗の言語化がうまい。
失敗を修正する前に、まず“表現”として肯定する。
この姿勢こそ、曖昧さの中で生き延びる術かもしれない。
「焼き加減」という言葉の中には、“加減”という不思議な単語が潜んでいる。
理科的に言えば、熱量のコントロールを指す。
けれど実際の現場では、
**「今日はこのくらいでいいか」**という人間的な投げやりの別名だ。
おそらくパンは、人間のこの“適当さ”を好む。
完璧な焼き時間を設定しても、湿度が違えば全てがズレる。
科学がどれだけ進歩しても、「いい匂いがしたら焼けた」で終わる。
パン作りとはつまり、測定をあきらめた科学である。
それでも、人はパンを焼く。
曖昧な結果を、毎日確かめる。
「昨日より少し焦げたな」と思いながら、
「でも今日はこれでいい」とも思う。
焼き加減は、正解ではなくその日の気分の翻訳だ。
パンはきっと、人間のあいまいさを笑っている。
オーブンの中で、まるで心の温度を測っているみたいに。