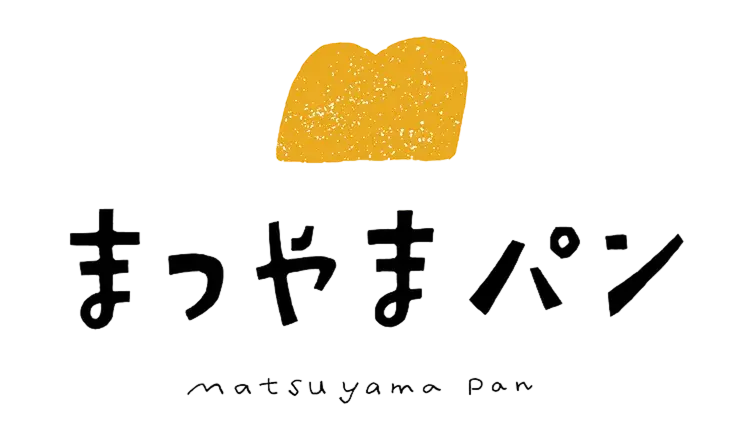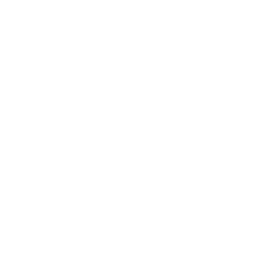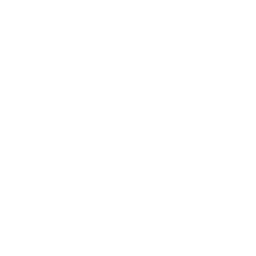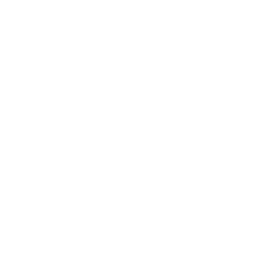小麦の奴隷になるまでの人類史──キューブパン店主が読む『サピエンス全史』
小麦の奴隷。なんとも挑発的な言葉だ
「小麦の奴隷」という名前をホリエモンさんがベーカリーチェーンにつけたと知ったとき、
正直すこし笑ってしまった。
パン屋である私からすると、なかなか刺激的な名前だ。
しかも『サピエンス全史』の帯コメントまで書いているのだから、引用元はほぼ間違いない。
とはいえ、「奴隷」という言葉を軽々しく使えるのは、
ホリエモンさんらしい。普通のパン屋ではなかなか選ばない。
でも、考えてみれば、朝から晩までキューブパンを焼いている私たちは、
すでに小麦の支配下にあるのかもしれない。
文明のはじまりからこっちは、人類はずっと小麦に操られてきた。
この文章を書きながらも生地の発酵具合が気になり、結局小麦の顔色をうかがっている。これを「奴隷」と呼ばずして何と呼ぶのだろう。
人類が農業を“発明”した瞬間は、案外ドジだった?
『サピエンス全史』によれば、人類が小麦を育て始めたのは、
壮大な実験というより、ちょっとしたドジの延長らしい。
狩りの帰りに抱えていた麦束をうっかり落とし、気づいたら芽が出ていた。
それを見た誰かが、
「これ、撒いておけば無限に生えるのでは?」
と発見してしまった。
私もたまにキューブパンの粉袋をひっくり返すことがあるが、
そこから文明が生まれる気配はまったくない。
そう考えると、古代の人類は相当な観察力を持っていたか、
あるいは暇だったのかもしれない。
そして気づいたのだ。
「麦って、獲物と違って逃げないじゃん」
「しかも長く保存できるじゃん」
狩猟採集の不安定な生活に比べたら、これは非常に魅力的だ。
今日獲れなかったら明日がない、というリアリティが続く生活は、精神的にしんどい。
パンの原型に近い“焼いた穀物の塊”は、当時の人類にとっては命を支える安定剤だった。
現代のキューブパンが“贈り物”のイメージを帯びているのとは、少し対照的で面白い。

農業は人類を豊かにした? それとも小麦を豊かにした?
農業は便利だ。便利すぎて、人類はあっという間にそこに依存した。
収穫量は増え、人口も増え、村は町に、町は文明へと変わっていった。
しかし、『サピエンス全史』の著者ハラリはここでひねりを入れる。
「繁栄したのは人類ではなく、小麦である」と。
事実、小麦は世界中に広がった。
植物にとって“繁栄”とは生息域が広がることだ。
つまり、小麦から見れば人類こそ最良のプロモーターであり、労働力である。
畑を耕し、雑草を抜き、害獣を追い払い、雨が降らなければ水までやる。
どちらが主体で、どちらが従属なのか、よく分からなくなる。
パン屋をやっていても、この図式は妙にリアルだ。
私たちは小麦を加工しているつもりだが、実際には毎日、小麦に人生を調整されている。
気温が高い日は発酵が早すぎるし、寒い日はのんびり構えてくる。
こちらの都合は一切聞いてくれない。
こうして人類は、小麦のスケジュールに合わせた生活に組み込まれていった。
いわば、小麦という植物の管理下にある高度な生命体。それが私たちだ。
パンは人類の知性なのか、それとも服従の証なのか
小麦を育て、粉にし、こねて、発酵させ、焼く。
この一連の工程は、人類の知性と技術の結晶でもある。
火の扱い、発酵の理解、温度管理。
そう考えると、パンづくりは人類の偉業と言える。
一方で、こう言えなくもない。
「小麦にこんな面倒な作業をさせられている」と。
キューブパンもその一つだ。
四角い型の中に生地を閉じ込め、膨らみ方を制御し、断面の気泡までこだわる。
これはパン屋の技術と情熱の象徴だが、
小麦視点で見れば「そこまでして私を食べたいの?」という話になる。
文明とは、パンをより美味しく食べるための巨大装置なのかもしれない。
人類がパンを選んだのか、パンが人類を選んだのか
振り返ってみれば、人類はパンを作り続け、小麦を育て続けてきた。
そして今、私はキューブパンを焼き続けている。
原始の麦束を抱えて歩いた誰かと、オーブン前で発酵のタイミングを見極める私のあいだには、1万年以上の時間が流れている。しかし、小麦との関係は驚くほど変わっていない。
結局、私たちは小麦と共犯関係にあるのだ。
「小麦の奴隷」という言葉は、皮肉のようでいて本質を突いている。
人類がパンを作っているのか、パンが人類を動かしているのか──その境界は曖昧だ。
ただ一つ確かなのは、明日も私はキューブパンを焼くだろうということ。
そして焼き上がった香りは、また誰かの生活をほんの少しだけ豊かにする。
奴隷かどうかはさておき、それは悪くない関係だ。