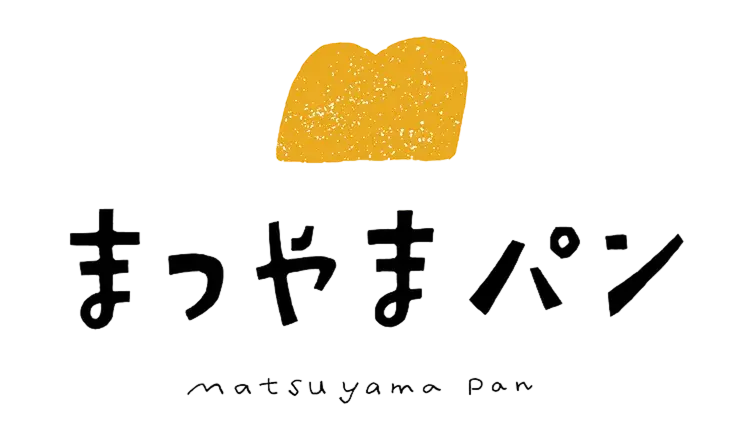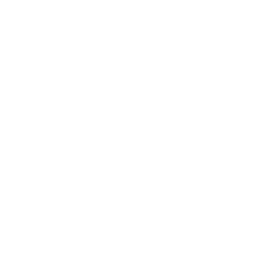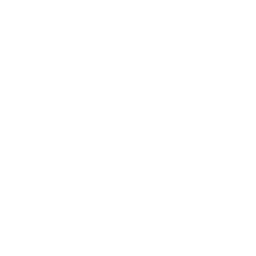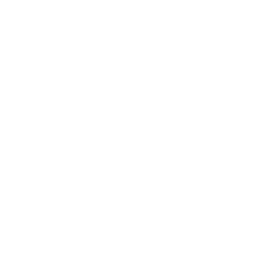パンを味わうという教養|テイスティングがひらく世界
パンは、ただ食べるだけのものだろうか
パンは日常の食べ物だ。
特別な準備もいらず、難しい知識がなくても食べられる。
だからこそ、私たちは長いあいだ、パンを「考える対象」から外してきたのかもしれない。
けれど、本当にそうだろうか。
ワインやコーヒー、日本酒のように、
パンにも味わい方があり、読み解き方があり、背景がある。
この連載では、
パンを「じっくり味わう」ためのテイスティングという視点から、
その奥行きを順に見てきた。
見ることで、パンは語り始める
第1章で扱ったのは、観察だった。
外観、触感、断面。
まだ口に入れていない段階でも、パンは多くの情報を持っている。
焼き色は、どこまで火を入れたかを教えてくれる。
ふくらみ方は、生地の軽さや密度を想像させる。
断面の気泡は、発酵の履歴そのものだ。
ここで大切なのは、
正解を当てることではない。
「読む姿勢」を持つことだ。
パンは、黙っていても、よく見る人には多くを語る。
味は、時間とともに立ち上がる
第2章では、感覚に踏み込んだ。
香りを嗅ぎ、噛み、溶け、余韻を感じる。
パンの味わいは、一瞬で決まるものではない。
アロマとフレーバーを分けて考えることで、
香りの層が見えてくる。
前歯と奥歯で役割が違うことを意識すると、
食感の情報量が増える。
噛むほどに甘くなるのは、
生地が唾液と混ざり、分解されていくからだ。
パンの味は、
空間ではなく、時間の中で立ち上がる。
それに気づくだけで、食べ方は大きく変わる。

比べることで、理解は立体になる
第3章では、比較を行った。
食感の軽重と、香りの濃淡。
2つの軸を置き、バゲットをマトリックスで整理する。
1つのパンだけを食べても、
その位置はわかりにくい。
しかし、数が増えると、
頭の中に地図が描かれていく。
このパンは、軽い側か。
香りは、どのあたりにあるか。
比較することで、
味わいは言葉を持ち、理解に変わる。
そして、
どこにも収まらないパンに出会ったとき、
私たちは強く惹きつけられる。
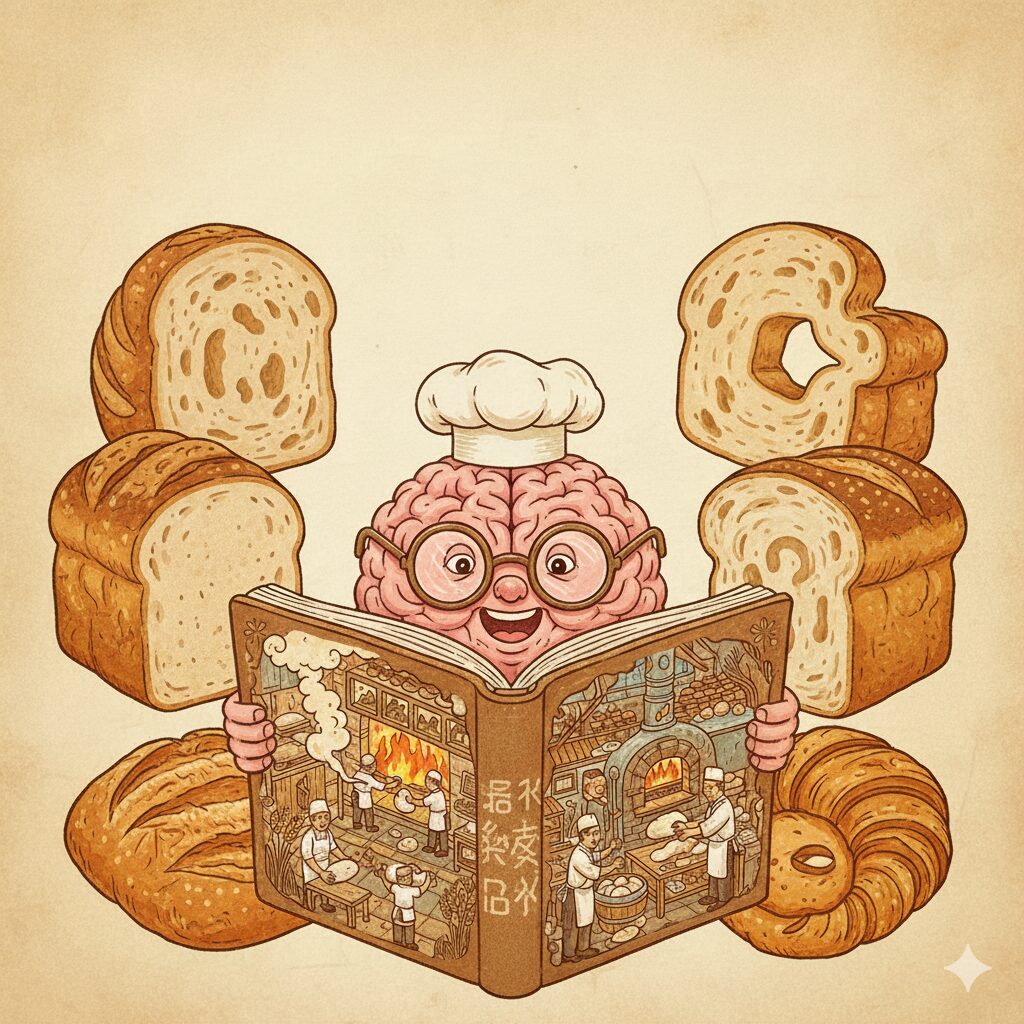
テイスティングは、選ぶ力を育てる
パン・テイスティングは、
専門家のための技術ではない。
むしろ、
自分の感覚を信じて選ぶための道具だ。
今日は軽い気分か。
今日は発酵を感じたいか。
今日は、安心したいか。
そう考えながらパンを選べるようになると、
食べる行為そのものが、少し豊かになる。
パンを読むという楽しみ
パンを味わうことは、
作者の意図や、素材、発酵の時間を想像することでもある。
それは、
完成品だけを見るのではなく、
そこに至るプロセスを含めて楽しむということだ。
アートを鑑賞するときの感覚に、
どこか似ている。
パンは、読むことのできる食べ物だ。
そして、テイスティングは、その読み方の一つにすぎない。
日常の中で、少しだけ立ち止まる
パンは、これからも日常にあり続ける。
だからこそ、
たまに立ち止まって、じっくり味わってみる。
見る。
嗅ぐ。
噛む。
比べる。
それだけで、
いつものパンが、少し違って見えてくる。
キューブパンのように、
見た目と中身にギャップのあるパンなら、
なおさらだ。
パンをテイスティングすることは、
特別な知識を増やすことではない。
自分の感覚を、取り戻すことなのかもしれない。